六座町
六座町の名は、蛎久から天満宮とともに市場が移されたとき、穀物座・木工座・金銀座・縫工座・煙硝座・鉄砲座の六つの座ができたことから由来しています。

六座町(ろくざまち)
所在地:佐賀県佐賀市六座町
佐賀藩祖・鍋島直茂は、鍋島の蠣久から呼び寄せた独占的な商人の集団「座」を設けました。それを当時は六座と呼び、町名として今に伝わっています。

長崎街道の北面天満宮がある通りの近辺です。六座町の名は、蛎久から天満宮とともに市場が移されたとき、穀物座・木工座・金銀座・縫工座・煙硝座・鉄砲座の六つの座ができたことから由来しています。
六座町は佐賀城下で一番古い歴史を持った町で、市場発祥の地として長崎街道佐賀城下の繁華街でした。現在は、「○○座跡」と記された木の柱の様なものが建っています。
また、六座町の方々がまちづくり活動として、六座町の街道沿いに花を植える運動などをされています。散策途中に、様々なお花に癒されます。

北面天満宮の縁起と六座町の由来
北面天満宮は、むかし、鍋島町蛎久が肥前の国府であった頃、市場に鎮座の一国一社の天満宮を佐賀城下の町づくりの際、鍋島直茂が蛎久の市場と共に当地に移してしまった。当時蛎久で神社の諸事を司っていた天徳寺住持、竹庵西堂は藩主の命を受け豪族右近刑部その他有力な人々とともに天正3年11月25日(1575年)神霊をこの地に移してまつり現在に至っている。以来天満宮は文教の守護神として又、火災除けの神として住民の崇拝厚くその実りとして六座町には今日まで大火災はないと言われている。
現在の神殿は貞亨3年(1686年)拝殿は元禄15年(1702年)改築されたものである。又、所蔵の大太鼓は慶長11年(1686年)製作され石の鳥居いは明應4年(1658年)の建立となっている。
六座町の名は、蛎久から天満宮とともに市場が移されたとき穀物座、木工座、金銀座、縫工座、煙硝座、鉄砲座の六つの座ができたことから由来している。六座町は佐賀城下で一番古い歴史を持った町で、市場発祥の地として長崎街道佐賀城下の繁華街であった。(現地案内板より)

穀物座跡

穀物座跡

木工座跡

木工座跡

金銀座跡

金銀座跡

縫工座跡

煙硝座跡

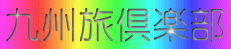
 佐賀
佐賀 唐津
唐津 武雄・嬉野
武雄・嬉野 有田・伊万里
有田・伊万里 鳥栖・三養基郡
鳥栖・三養基郡 多久・神崎
多久・神崎 えびす
えびす