生月島
長崎県の平戸島の北西にある、面積16.57平方キロメートルの島です。

南北約10km、東西約2kmの南北に細長い形をした島です。平成3年(1991年)に生月大橋が開通し、平戸島と結ばれました。

遣隋使・遣唐使の時代に中国から日本へ帰国する旅人が、船上からこの島を見つけると、「無事に帰ってこられた」と安心して、「ほっとひと息をついた」ことから、生月(いきつき)島と名付けられたといわれています。

道の駅 生月大橋
所在地:長崎県平戸市生月町南免4375-1
営業時間:8:30~17:30
休館日:12/31
生月大橋の生月町側にあります。

平戸名物のアゴや海産物やガラス細工などを販売しています。

道の駅生月大橋には、生月の観光案内所があります。

大氣圏
所在地:長崎県平戸市生月町南免4432-101
本場 あごだしラーメンの店です。

生月特産のあごだし(生トビウオの炭火焼、天日干し)を使って、時間をかけて丁寧にとられた黄金の透明スープとちぢれ麺は相性抜群です。香ばしく風味豊かな高級あごだしスープはあっさりだけどコクがあります。

潮見神社
所在地:長崎県平戸市生月町南免4364番地
御祭神:七郎皇子
潮見神社に祀られている七郎神については従来、仲哀天皇の御孫・十城別王の家来だとされてきましたが、『神社帳抜書』(江戸時代)の平戸の七郎神社の項には、七郎大権現は仲哀天皇当時の左大臣・別氏(和気氏の事か)の嫡子で、神功皇后に従い「三韓征伐」に加わり帰国した後、天平10年(738年)に神として「出現」したとされます。その後、天応10年(790年)の遣唐使の派遣に関連して「紹法七郎大権現」の勅額が下賜されたとされますが、ここに登場する「紹法」という名称については、中国で宋?明代初頭に信仰された「招宝七郎」という神に由来する事を、二階堂善弘氏が明らかにされています。(生月学講座NO.124より)

蟇股

木鼻の獅子と象


鷹ノ巣トンネル
サンセットウェイ生月農免農道にあります。

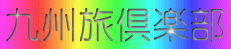
 長崎
長崎 平戸
平戸 佐世保
佐世保 島原
島原 雲仙・小浜
雲仙・小浜